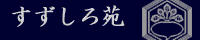コイノヤマイ Ver.Y - すずしろ苑/聖護院ひじりさま
In respect for コイノヤマイ/ハヅキ and 恋愛依存症の彼/天野かづき
目覚めたユーリは、まず、朝にしては強すぎる陽の光に戸惑いを覚えた。それからじっと覗き込んでいる護衛の顔。探るような、労わるような。何事か言いたげな視線がユーリを見つめて。
ユーリは。
その瞬間から、コンラートがすべてになった。
「これはそういう病気なのです」
「まるで雛の刷り込みだな」
発病して初めに出会った相手に、まるで恋のような執着を持つのが症状なのだと――ギーゼラが説明すると、コンラートは呆然と呟いた。
まさに親鳥に寄りそう雛のようなユーリが、コンラートの手をぎゅっと握り直す。空いた方の手が、安心させるようにユーリの力んだ甲を撫でた。
だがユーリには、病気だと診断されてほっとする部分もあった。
怖いくらいの不安。この手を放しては、一秒とも生きていられない。そんな強迫的な心持ちも、病のせいだと言われると納得できたのだ。
この国の王になって百年ばかり。ずっと一番傍に居てユーリを支えてくれた相手だが、こんな、この手がなくては息もできないような気持ちになったのは初めてのことだ。
生死に係わる状況でもない、初夏の昼下がり。長閑と言っても良いくらいの日常で突然覚えた強すぎる執着。
ギーゼラの説明を聞くその熱心さに、嫉妬を抱いてしまうほどの。
「ユーリ、何を」
コンラートの耳を掌で塞いで強引に横を向かせる。視線の先にユーリだけがくるように。
「病に罹っているのはおれだ。一般的な症例なんか聞くより、おれを見ればいいじゃないか」
「無茶を言わないで」
「で、ギーゼラさん。これって治るの?」
こんな、嵐の中に放り出されたみたいな気持ち。押し寄せる何かに揉みくちゃにされそうな恐怖。
だけど少し、攫われてもみたいような期待も。治らなくったって、いい。この男を自分のものにしてしまえるのなら。
見つめる先のコンラートの視線がギーゼラの方へ流れて、不快感のままにぐっと身を乗り出した。
「ええ。治療法は確立されています」
困ったようなコンラートの視線が戻ってくる。
まるで話を聞く態度ではない二人には構わず、ギーゼラが淡々と説明する。
ハシバミ色に鈍く光る銀の光彩。瞳の中にユーリがいる。
「そう、あんたはおれだけを映していればいい」
「適切な対応で後遺症なく根治するので、陛下にはそのプログラムに従った治療を受けて頂く予定です」
ユーリの吐息がコンラートに当たって返ってくる。コンラートが小さく息をのんだ。
引き寄せられるように、更に近づいて。相手の体温を唇の先で感じる距離まで来て。重なる直前、二の腕を掴んで距離を取られた。
「無理矢理引き離したり、監禁したりという措置は有効ではありません。むしろ害、場合によっては精神に異常をきたし、生命の危険もあります」
「えっ」と、拘束が緩む。
すかさずユーリは肩を押して、後ろへ倒れ込むコンラートの上に乗り上げた。
「かといって患者につきあって合わせてやるというのもこのような――陛下とウェラー卿のような、病が癒えた後も人間関係が続くような場合は。大変気まずいことになるでしょうから」
かろうじて腕を胸の間につっかえさせて押しとどめられる。不利な体勢といえども職業軍人のコンラートと、三十センチを巡って攻防を繰り広げる。
「そこはウェラー卿のさじ加減で。得意でしょう?のらりくらりとかわすのは」
ちょっと冷たいギーゼラの台詞に、コンラートの眉が情けなく下がった。
隙あり、と押しきったら、腕を払われて。勢いのままぐるりと視界が廻る。気がつけば椅子の上にうつ伏せに押し付けられていた。
どういう加減か素人のユーリには判らないが、後ろ手にさせられた腕を押さえられているだけでまるで身動きが叶わない。
「今後の陛下の身心の御健康は、すべてウェラー卿次第です。しっかり頼みますよ」
不自由な体勢で仰ぎ見ると、コンラートは酸っぱいものでも食べたかのような顔をしていた。だけどどうやら一緒に居られるらしいと、ユーリはそれだけで嬉しくなった。
夏用の薄手の上着なのに肩に重く感じる。着替えを手伝ってくれている護衛に、ユーリは拗ねたような顔で食い下がってみたけれど。
「治療も兼ねているんですから。お判りでしょう?」
コンラートなしでは息もできない。そんな病的な執着は一週間もして少し、落ち着いてきた。
手を放すこともできない最初の三日。同じ部屋にいるならばちょっとくらい離れても大丈夫な次の三日を経て、今日は初めてコンラートとは別で謁見に臨む。
執務室に籠っている分には膝抱っこでも問題は無かったが、さすがに謁見ともなれば大いに差し障りがあるわけだ。
これまで先延ばしにしてきたそんな仕事にしぶしぶ向かう。
ギーゼラの言った治療法とは、段階を経て徐々にコンラートから引き離していく、というものだった。
「母親にべったりの乳飲み子が成長に合わせて徐々に親離れしていく様に似ているかもしれませんね」と彼女は称したが。だったら今日のは、母親が用事で、初めて隣のおばさんに預けられたりする状態なのかもしれない。
「がんばったら後で甘えさせろよ」
それこそ幼児だけど。
「ええ。がんばったらね」
「キスしてくれる?」
「それは勘弁」
子供から逸脱する分には、コンラートはにっこり断わりを口にする。
「いい加減に諦めろよ」
「無理ですってば。甘やかすのはいくらでもして差し上げるけどね」
この一週間ですっかり慣れた風に頭を撫でられる。
つきっきりで幼い子の世話をするみたいに、べたべたとはしてくれたって。コンラートはきっちり引いた線を絶対に越えない。
「あんたって相当ひどいよね」
「病気のせいで言ってるんだと許してあげます」
さぁ行きましょう、と促されて、部屋を出る前にその存在を記憶するようにコンラートの手を握った。
あぁ、この手が。頭を撫でるだけでないといいのに。
はたから見ればぬるい笑いしか浮かばないような遣り取りをコンラートと繰り返しつつも、ユーリの治療は順調に進んでいった。
昼間のほとんどをコンラートと離れて過すようになって、その埋め合わせのように許可されている時間は近くに居たくなる。
長椅子の端に掛けたコンラートの膝に頭を預けて転がって、見上げる先には見慣れた瞳。
ずっと吸い込まれそうなくらい不思議な色彩だと思っていたけれど、一緒に居た百年分と同じくらいを病を得てから見つめている。
届きそうで届かない、三十センチを隔てて。
静かな宵。静かなコンラートの表情。
代償を求めず甘えることを許してくれる、母親のような。
ぐっと喉元にせり上がる苦しさに負けてユーリは零した。
「あんたになら抱かれたっていいよ」
髪を撫でていた手が滑ってユーリの視界を塞いぐ。
「馬鹿なことを言ってないで。お疲れでしょう、このまま眠って構いませんよ」
熱くなりそうな目元を押さえてくれるのは好都合だった。決して滑らかではない、硬い角質も傷跡もある掌を感じて闇に身をゆだねる。
疲れているのは本当だ。コンラートなしで過せる時間が長くなるにつれて内に抱える我慢も大きくなっていった。
これまでは躊躇なく求めていられたのに、分別だとか思慮だとか余計な知恵が邪魔をする。困らせたくない、嫌われたくない、なんていう計算も。
罹患してすぐの頃ならこんな風に大人しく聞き流されてなんかいない。実は当て身を喰らわされて、気がついたら朝だった、なんてことも何度かある。
快方に向かうに従って、徐々に取り戻す理性がユーリを苦しめる。
コンラートの姿がないだけで気が狂いそうになる不安感はなくなったけれど。こんなに辛いならばいっそ病気のままでも構わない。ついそんなことを思ってしまうほどに。
それとも、完全に癒えたらこんな痛みすら無くなるのだろうか。
考えてみたけれどあまり気持ちは休まらなかった。今の苦痛が大きくて治った時のことなど想像つかないせいか、それとも。
心を疲弊させる屈託とコンラートがもたらす安寧とに、ユーリは徐々に眠りの淵に引きこまれる。
「親離れなら親子の情は残るのにね」
ユメウツツにそんな呟きを耳にした気もするけれど、意味を考える前にこぼれ落ちてしまった。
「あなたはまだ俺とキスしたいですか」
唐突なそんな質問がコンラートから発せられたのは、ギーゼラから完治を告げられて数日も経過した午後だった。
王佐も宰相も外した執務室にコンラートが居たのは、単に護衛としてだけで。それは病気とは関係の無い以前からの習慣だった。
整理を頼んでいた書類をユーリのところまで運んで来て。終わりましたよ、の代わりにそんな言葉。
「したいよ――ありがとう」
ユーリは書き物から顔も上げずに返す。
何かに追い立てられるような焦燥は確かに癒えた。なのにコンラートに覚えた執着はそのままだ。
ひょっとしたら完治しなかったのかもしれない。だけど。ならばそれでもいいかと思っている。
百年間、ユーリの一番近くでユーリを護ってきてくれた人。それだけじゃなくて、魔王だとか護衛だとかいうのを越えて親友だと思ってきた。とても大切な友情が病気のせいでちょっと変性して。もっと粘着質なものになってしまっただけ。
たとえば新しい彼女が出来たら、今までだったら良かったじゃん、上手くやんなよね、なんて言って。出来たての彼女がいるのにあんま連れ回したら悪いかなー、って思う時にちょっとつまらなく感じてたのが。――あー、想像するだけでダメ。たぶん、無理。
そんなことを考えていたせいで、手を止めてコンラートを見上げた目つきは随分きついものになっていた。
でもって、なんでそんな無神経なこと聞くかなぁ。折角なんとなく納得させているのに。
「しましょうか、キス」
「え?」
何でもないことのようにさらりと提案されて。
「あれほど嫌がってたのになんで今更」
「だってあれは病気のせいだったんでしょう? そんなの、切ないじゃないですか」
「切ないって?」
思いもしなかった台詞を聞いた。聞き返すのには曖昧な笑み。期待するのが怖い。
「病は治ったのに。あなたが俺とキスしたいっていうのはどうして?」
答えくれないで、逆に問い返される。
「拒まれ続けたもんだから諦めきれないのかも」
「じゃあいっぺんやってみたら気が済みますか」
かもね、と苦笑しては見せたけど。なわけあるか。でも。
コンラートが寄越した挨拶みたいに軽く重ねただけのキスに、喉から心臓が飛び出そうなくらいにドキドキした。
耳たぶをコンラートの指が撫でて、肩が揺れる。真っ赤になっているのを笑われているんだろうけど。
「憎からず思っている相手に好きだ好きだと言われ続けて、その気にならない訳がないでしょう」
この性悪おやじめ。それまで欠片も見せなかった顔が言う。
「その割にこっぴどく振り続けてくれてたよな」
「だからあの時はあなたの病が言わせてたんでしょう? 治った瞬間、無かったことに、なんて言われたら耐えられないじゃないですか」
「そういう奴だよあんたって」
ちょっとは申し訳なさそうにしてもいいんじゃないかと思う。
「で。どうでした。気が済んだ?」
否定することなど毛頭考えてない風に誘われて。だけど百年も親友として付き合ってれば、そんな奴の性質の悪さぐらい今更問題ですらないわけだ。
「素直に惚れたって言えよ」
白々しくコンラートは目を丸くして見せた。
「あなたこそ。素直じゃないですね」
ユーリを魅了して止まない銀色の星が間近に迫る。
「それに正しくは、ほだされた、ですよ」
吐息が触れる距離でご丁寧に付け加えるのに、もう黙れ、と伸び上がった。
聖護院ひじりさまより頂きました!
お正月にお会いした時に天野先生のご本を押し付け、いかに萌えるかを語りまくってから早半年、ひじりさんに書いてもらえました!
ユーリに迫られても手が出せない次男というシチュエーションに激しく萌えます。
ありがとうございます、ありがとうございますヽ(´▽`)ノ
(2011.06.28)